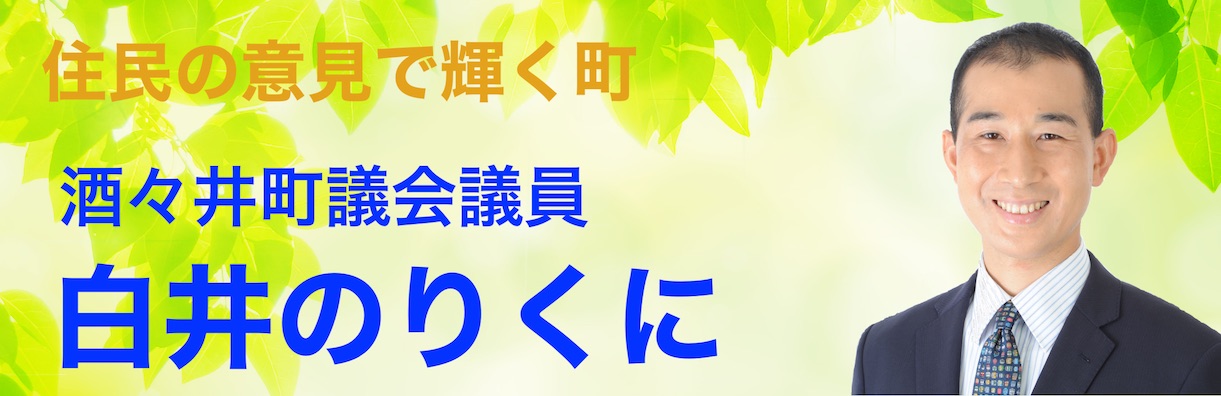2023.9.25 「税理士、司法書士ら専門家が消費税・インボイス制度への認識を問う公開質問状 記者会見」
昨日9/25は、「税理士、司法書士ら専門家が消費税・インボイス制度への認識を問う公開質問状 記者会見」に登壇しました。

司会が、神田知宜(税理士)
登壇者は、以下の通り。
湖東京至 (元静岡大学教授 税理士)
白井則邦 (酒々井町議会議員 司法書士)
安藤 裕 (元自民党衆議院議員 税理士)
佐伯和雅 (税理士)
私は2回発言させて頂きました。
5:01〜 挨拶と正確な報道のお願い
28:49〜 消費税が生活再建へ悪影響を与えるという点を説明。
資料は下記リンクにあります。
https://drive.google.com/drive/folders/123Bp4WYcIHpjK1jECy8N6EYgLFaXK-CA
冒頭の挨拶の中で、誤った報道により、当事者が言われなき中傷を受けることがないように、また民主主義国家の意思決定を歪めることがないように求めました。
生活保護バッシングを事例としてあげたけど、もしかしたら共感を持って聞いてもらえない事例だったかもと、後から反省。
消費税が生活再建へ悪影響を与えるという点で、
・挟んでも消えない非免責債権であること
・公租公課には延滞税が年14.6%かかること (※)
・強力な調査権限があることを
説明。
また、消費税納税義務があると分からずに登録したり、勝手に漏録されてしまい、数年分滞納になり、支払い不能になる可能性があるのではないかと問題提起しました。
※正確には、「年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合。
2025.5.11追記
私の当日の原稿をアップしていなかったので、追記しました。
インボイス制度の導入により、個人事業主の生活再建が難しくなる?
1.消費税は、破産をしても残ってしまう「非免責債権」
債務を負った人が自己破産をすると、基本的には債務は免責され、返済の必要がなくなります。しかし、例外的に破産をしても免責されない「非免責債権」というものがあります。その中の一つが、税金や社会保険料といった「公租公課」です。消費税は当然ながら税金ですので、免責されません。
2.消費税は赤字でも課税される
消費税は、売上にかかる税ですので、経営が赤字であっても納税の義務が発生します。
零細事業者は、消費税納税に必要な正確な帳簿作成を期待できなく、赤字でも納税義務を免れない消費税納税の負担に堪えられない可能性が高いからこそ、免税事業者とされています。ところが、インボイス制度は、今まで免税事業者であった事業者を課税事業者へと変えてしまいます。これまで課税事業者でなかった者に消費税の納税義務を課すことになるインボイス制度は、必然的に免責されない消費税を負わせることになるため、破産後の生活再建の妨げになる可能性が高いのです。
3.滞納した租税の徴収
租税を滞納すれば、延滞税がかかります。延滞税は、納期限の翌日から2か月を経過した日以後は、原則として年14.6パーセントと大きな負担となります。分納しようとしても、延滞税がドンドン加算されてしまい、完納まで膨大な時間がかかったり、または完納を諦めざるを得ないことは少なくありません。租税滞納は、人生に一生ついて回る危険があるのです。
更に、通常の私人間の債務とは違い、債務名義がなくても差し押さえができます。また、民間よりも広範かつ強力な調査権限を有しており、例えば銀行に対して、裁判所の関与無しに、預金調査として個別照会および全店照会ができます。また、滞納者の預金口座を特定するだけでなく、口座の取引履歴も知ることができます。
このように滞納処分は強力であるため、謙抑的な運用が求められるにもかかわらず、違法な執行が行われることがあります。国ではなく、地方自治体の事例ですが、取引履歴から、差押禁止債権である児童手当が入金される時期を確認してから、児童手当が銀行に振り込まれたタイミングで滞納処分による差押えが行われ、後に裁判所により違法と認定されたケースがあります。
4.インボイス制度がもたらす生活再建への影響
消費税は滞納額も多く、令和3年度では滞納額 8857 億円中 3551 億円が消費税です。もし個人事業主が破産をした場合、消費税課税事業者であれば、消費税が非免責債権として残る可能性は高いと考えられます。破産をして新たな人生をやり直そうとしたとしても、租税が残っていたらその妨げになってしまいます。
小規模零細事業者の破産は、今でも租税の滞納があることがあり、生活再建に苦しむことが少なくありません。インボイス制度が開始されれば、課税事業者になることを強要され、生活再建に苦しむ方が増えることは明らかです。新たに事業を始めたい、チャレンジがしたいと考える人が二の足を踏むのではないでしょうか。
5.インボイス制度導入直後に注意すべき問題
インボイス制度は、その必要性が吟味されることなく導入が決まり、不必要に複雑な制度設計でありながら、適切な情報提供がされてきませんでした。また、インボイス導入によって直接不利益を受けるのは、免税事業者からの仕入れ税額控除できなくなる課税事業者です。そのため、インボイス登録が強要される危険性が高い精度と言えます。
導入直後に問題となるのは、①消費税の課税義務が発生することを知らずに、取引先や税理士に促されてインボイス登録してしまった方、②知らないうちにインボイス登録されてしまった方だと考えられます。
②については、あり得ないと思う方は多いと思います。しかし、X(旧Twitter)に「税理士に勝手に登録されてた」という事例が挙がっています。また、偽装請負、偽装委託で働いている労働者も、勝手にインボイス登録される危険性が高いと考えられます。偽装請負、偽装委託とは、雇用だと労働法が適用されるが、請負、委託は労働法の対象外のため労働法制を無視した対応が可能のため利用されます。また、雇用だと消費税の仕入税額控除はできないが、請負・委託は仕入税額控除できる。更に請負・委託だと、保険料の企業側負担を免れる。このような企業側の一方的なメリットから、実態は雇用でも、請負・委託として扱う企業がある。本来は違法だが、労働者が、自分が雇用契約ではなく、請負契約や委託契約になっていることを知らないことも多い。
いずれも本人が、インボイス登録し消費税の申告義務が発生することも納税義務が発生することもよくわからないケースです。こういう方々は税務署から資料などが届いても封も開けずに放ったらかしのケースが少なくないと考えられます。そのまま放置した結果、3年とか4年が経ったときに税務署から連絡がきて、滞納税額が百万円を超える金額になっているなど、到底支払えない状況に陥ることが考えられます。今までの事例とは全く違う消費税滞納問題が生じ、非免責債務の問題が全国で爆発的に増えると可能性があります。
このように、インボイス制度導入により、今まできちんと生活できていた方が、予期せぬ消費税滞納により、再起不能な状況に追い込まれる可能性があるのです。