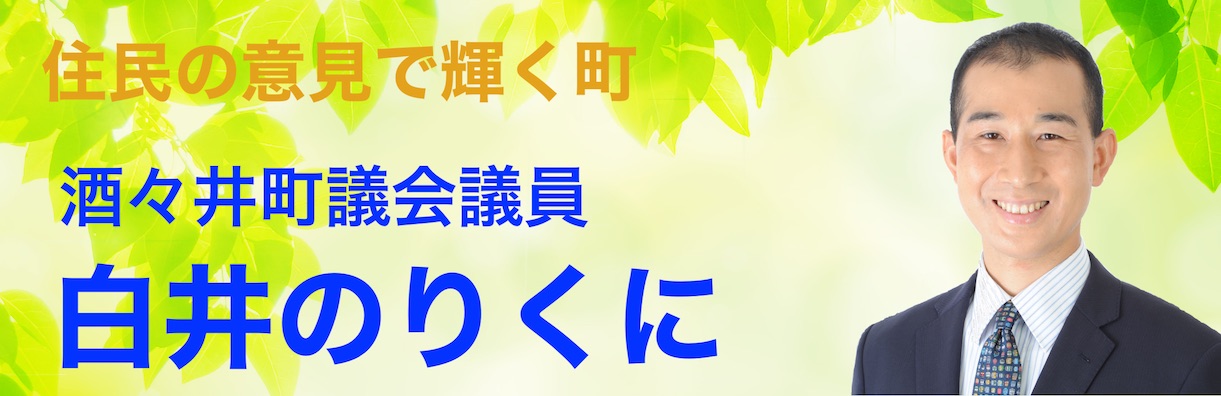2024年12月議会 一般質問「消費者保護施策について」
2024年12月議会では、一般質問として「消費者保護施策について」を質問しました。なお、本文中のQ&Aは、「Whisper Transcription」を使った自動文字起こしを利用しています。正確な文言は、酒々井町議会の議事録をご参照ください。
(※ 参照 酒々井町議会 議事録の検索)
高齢者を対象とした訪問販売、電話勧誘販売の被害、インターネット販売のトラブル、20代を中心としたマルチ商法被害の増加など、消費者被害は、現在も相次いでいる。他にも、「オレオレ詐欺」をはじめとする特殊詐欺の被害はまだ多く、また、スマホ利用の低年齢化により、小中学生が数十万円の課金をして、高額の請求をされる相談事例も増えています。
消費者被害が生じることは、経済的損失、精神的打撃、健康への被害が生じることの他、特にマルチ商法などに取り込まれると、家族・友人関係が崩壊するなど、社会生活に大きな影響を与えます。
消費者保護施策の充実は、行政にとって長年の課題であり、また新たに生じる消費者被害に対応するために迅速な対応も必要です。
そのような状況の下で、千葉県は、本年3月に第4次千葉県消費者生活基本計画をまとめました。
(※ 参考 第4次千葉県消費生活基本計画の策定について)
計画の基本施策として
1,消費者被害の防止、救済とネットワーク強化、
2.消費者市民を育む教育の推進、
3、安全安心な消費生活の確保
という3点があげられています。
具体的な目標がいくつか掲げられており、例えば、認知症等の高齢者や障がい者等の消費者トラブルの未然防止や被害の拡大防止に取り組むための「見守りネットワーク」の整備について、昨年末で県内36市町村のところ、令和10年の目標として全市町村での整備を掲げています。
このような消費者被害の現状や、千葉県の計画があることを踏まえて質問しました。
Q 消費者保護政策として、消費者教育・相談・見守りネットワークの構築など様々な取組が考えられるが、酒々井町ではどのような取組をしているのか。
A1 【町が取り組んでいる消費者保護施策】
専門の相談員による毎週1回の消費生活相談を役場会議室で実施しており、消費者からの相談に対して適切なアドバイスや情報提供を行い、問題解決に向けたサポートをしています。特に訪問販売や通信販売に関する相談が増えていることから、これらの問題に対する相談員のスキルアップのため、積極的に研修会への参加を行っています。
また、啓発活動として広報入試数を活用し、相談事例を踏まえた消費者が注意すべきポイントや、相談窓口の利用方法について修正を行っています。
さらに、公民間の利用団体によるオープンセミナーとして開催される消費生活トラブルに関する講座への講師派遣も行っています。
なお、高齢者や障害者等の消費生活上、特に配慮を要する消費者を見守るため、見守りネットワーク等の整備については、先進市町村等の取組を調査・研究し、検討してまいりたいと考えております。
A2 【小中学校における消費者教育の取組】
学習指導要領において、消費者教育に関する内容が含まれており、社会科や家庭科の授業で扱います。
また、デジタル化の進展により、デジタル取引に伴うトラブルも増えていくことが予想されることから、授業を通して、また外部講師を招いたスマホ教室も活用しながら、購入や支払いの方法の特徴、売買契約の仕組みなどを理解し、必要な情報を収集することができるように学習を進めているところです。
なお、特に小中学生の消費者トラブルは、家庭でスマホを使った場面が想定されることから、インターネット適正利用に係る保護者向け啓発動画の紹介について学校に依頼しております。 また、学校では、学校便りやチラシ配付などにより、保護者への啓発を進めていると聞いております。
見守りネットワーク」については是非とも、先進事例をしっかりと調査研究していただきたいと思います。
例えば、熊本県の北部に位置する、玉名市(たまなし)・玉東町(ぎょくとうまち)・和水町(なごみまち)・南関町(なんかんまち)では、1市3町が相互に連携を図りながら協力して消費者施策を実施し、「訪問販売お断りステッカー」等があらかじめ貼られていれば、事業者は訪問勧誘してならないという、訪問販売禁止の制度も定めています。
(※ 消費者法ニュース 1市3町の連携による消費生活安心条例の制定について(有償サイト))
また、滋賀県の野洲市では、「消費者安全確保地域協議会」という制度を利用して、悪質業者から警察が押収した名簿を元に、独自の「見守りリスト」を作成し、消費者被害に遭いやすい方に対して、能動的な見守り活動をしています。これの取組は、11月13日のNHKクローズアップ現代でも取り上げられました。
(※ 参考 クローズアップ現代」高齢者ねらう不動産詐欺 独自取材 “被害”連鎖の実態」初回放送日:2024年11月13日)
町の面談による相談は週一回であり、後は千葉県消費者センターでの電話相談か、面談による相談は、予約して船橋市まで行かなければなりません。電話相談では、契約書などの確認が大変なため、また図や書類を提示したの説明も出来ないため、適切なアドバイスをすることは簡単ではありません。対面の相談の充実を計る必要があります。先に挙げた熊本の1市3町の取組では、玉名市消費生活センターが広域窓口となり、1市3町の住民からの相談に応じる体制を取っています。酒々井町も、独自の相談日を増やすことはもちろん、広域連携も検討しても良いのでは無いかと思います。
消費生活相談員は、専門的知識を活かしたアドバイスをするほか、消費者と事業者間のトラブルに介在して、交渉を手助けしてくれる「あっせん」をしてくれます。このあっせんは無料で利用できる制度でありながら、実効性に優れています。例えば、隣の印西市の消費生活センターでは、相談したことで支払わずに済んだ金額や取り戻した金額は、令和4年度は1000万円にのぼります。
身近な相談窓口があればこそ、迅速な被害防止や被害回復が可能となります。
窓口の維持や、充実が求められます。
相談窓口の充実の方法として、PIO-NETの導入が考えられます。
PIO-NETは、全国の消費生活センターをネットワークで結び、消費者からの消費生活に関する相談の収集を行っているシステムです。相談を受ける場合に、PIO-NETがあれば、相談の類似事例や相手方事業者からの被害状況などが直ぐにわかり、適切な対応を取ることが可能です。逆に言えば、これがなければ、最新の相談事例がわからなく、適切な対応を取れない可能性があるのです。そこでお伺いしますが
Q 現在酒々井町にはPIO-NETがありませんが、導入を検討したことがありますか?
A PIO-NETについては、これまでも導入に向けて検討してきましたが、予算が確保できず、導入には至っておりません。消費生活相談情報については、現在、書籍や千葉県から提供される事例集等を参考としたり、また、千葉県消費者センターに電話で情報収集をして、相談事務に対応しております。
PIO-NETについては、全国的な消費者トラブルの傾向や問題点を把握しやすく、また、最新の相談事例から迅速な対応が可能となり、消費者行政には必要なものと考えているため、導入に向けて引き続き検討してまいります。
パソコン導入の費用が係りますが、消費者相談の質向上のためには、ぜひともご検討いただきたいと思います。