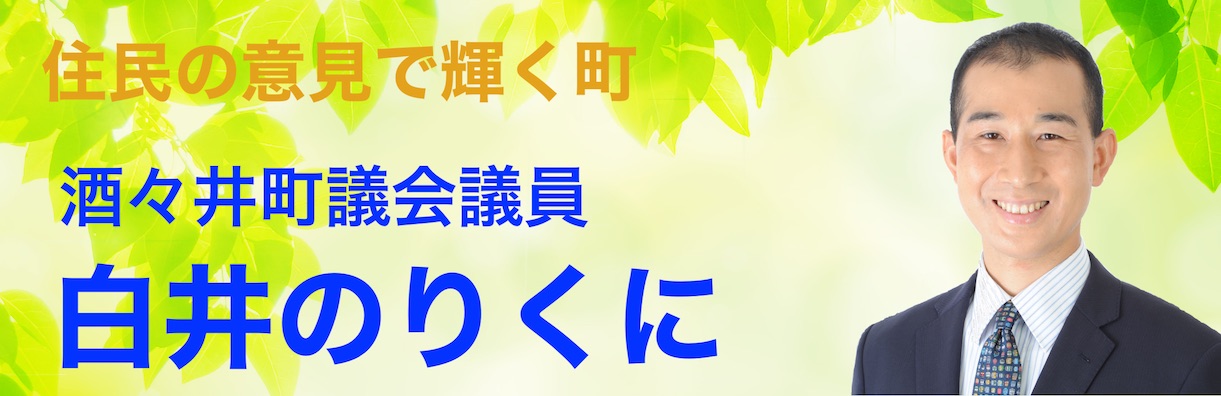2025.01.31 「第3期酒々井町子ども・子育て支援事業計画(素案)」へのパブコメを提出
2025.01.31 「第3期酒々井町子ども・子育て支援事業計画(素案)」へのパブコメを提出しました。
既に、意見募集のページが削除されているので、Xの投稿を上げてみました。
素案がないとわからないと思うので、素案も上げておきます。
下記が、送付した私の意見です。
●「子どもの意見表明権について」
子どもの権利条約、こども基本法やこども大綱に「子どもの意見の尊重」が謳われ、こども基本法11条に意見聴取の義務が設けられているにも関わらず、子どもの意見聴取がされていない。大人からの視点だけではなく、子どもからの視点も入れなければ、心身共に健やかな成長が出来ているかわからないのではないか。政策の評価や求める政策も、大人と子どもでは視点が違う。
また、P62に「子どもの意見を尊重する」と記載されているが、具体的な取り組みは計画されていない。P65以降に、具体的な施策として、「子どもの意見を尊重するため、子どもアドボカシーについて調査研究をする」などと記載をすることで、今後の取り組みを促すことも、計画策定の大事な要素だと考える。
●「青少年」という用語について
「青少年」という言葉を用いずに、「子ども・若者」という言葉を使うべきである。
「青少年」は、一般に普通に使われている用語であるが、「少年」という、男性に関する単語が使われており、意図せずに、男性の未成年・青年を中心とした政策や、女性を排除した政策であるという刷り込みがされかねない。
男尊女卑が当たり前だった時代の「父兄」と言う言葉から、「保護者」「親御さん」という言葉に変わったように、「青少年」という言葉ではなく、性別を含まない「子ども・若者」という言葉に変えるべきである。
●P3「計画作成の趣旨」
「少子化対策」というキーワードから始めるのではなく、「子どもの権利条約」の4原則や、「こども基本法」の6つの基本理念を最初に述べるべきではないか。子ども・子育て支援法第1条は「我が国における急速な少子化」という言葉から始まり、この計画は「少子化対策」としての計画という側面は否めない。しかしながら、なぜ、子ども・子育て支援が必要なのかといえば、子どもの人権を守るために、制度として子育て支援が必要であり、自治体はその義務を果たすために計画を策定するのである。これを忘れてしまうと、子どもの権利ではなく、大人の事情が優先された政策作りになってしまう。そのため、まず大きな理念を掲げるべきであると考える。
●P9〜 子ども・子育てを取り巻く状況
「子どもの貧困対策の取り組み」が計画にあるが、政策の基礎となるデータが、児童扶養手当の受給資格者数くらいしかない。これでは、貧困対策の取り組みが十分なのか確認するすべがない。所得階層分布のデータがあれば、格差が見えてくるし、所得と他の項目、例えば「子育てに対する感じ方」「子育てに関する情報の入手状況」などのクロス集計があると、困窮者対策の取り組みが足りているのか見えてくれることがあると思う。低所得者の数を見るとき指標となる他のデータとしては、就学支援利用者数、非課税世帯数なども考えれる。また、町内の子育て世帯における、平均所得と中央値などを掲載することで、町全体の状況を把握するということも一つの方法ではないかと思う。
一方で、所得に関するデータを公表することは、家庭の序列化を招き、差別の温床となるなど、負の作用もある。このため、掲載すべきとまでは考えないが、所得に関するデータを考慮して計画を作成する必要性は強調したい。
●P37の「病気やケガで教育・保育事業が利用できなかった場合の対処方法(就学前児童)」で、病児保育・病後児保育を利用したが、今回0%、前回2.0%というのは、かなり利用率が低い。他の自治体ではそれなりの利用者数があるため、町内に委託先がないということが大きな原因だと思うが、それならば、P44の「子育てしやすいまちづくりのために、重要だと思うこと」の選択肢として、「病児保育・病後児保育の充実」などの選択肢を設けることが、ニーズの把握として必要だったのではないか。次回以降に検討して貰いたい。
ただし、多くの就業先に「有休の、子の看護休暇」があるならば、病児保育・病後児保育はそこまで必要ではないと考えられる。基礎的なデータとして、父母が休んだときの「子の看護休暇」利用の有無、また「有休」「無休」の別が調査できると、その家庭における子どもの病気での対応のしやすさが見えてくる。またこのデータが所得階層分布と照らすと、所得階層による、子育てのしやすさが見えてくるかもしれない。
●P48 「ひきこもり対策の推進」
「ひきこもり対策の推進」として「不登校の児童生徒および保護者の相談を強化」というのは適切な記載なのか。
「ひきこもり」とは、外部との関わりを避け、社会から孤立することであり、学校に通えない不登校とは異なる。不登校からひきこもりとなる場合もあるが、それ以外の要因もある。「当事者および保護者の相談を強化」という記載にすべきである。
なお、別の箇所で記載するが、不登校児への対応は、独立して設けるべきである。
●P49 「子どもの貧困対策の推進」
「子どもの貧困対策の推進」の記載について
・経済的な理由等で生理用品を購入できない、いわゆる「生理の貧困」対策として、生理用品の無料配布をしているが、これは取り組みに記載しないのか。
・経済的な理由により高等学校等に進学が困難な者に対して奨学給付金を支給する「酒々井町奨学給付金」があるが、これは取り組みに記載しないのか。「就学援助」の記載もないため、学校に関する支援は記載しない方針なのかもしれないが、学校教育課ではなく、子ども課の事業のため、掲載することに問題はないと考える。
●P65〜「施策の展開」に、「不登校支援」の項目を設けるべきである。
不登校は学校の問題であるとして省かれているかもしれないが、不登校は学校だけで解決できる問題ではない。その背景には、経済的な貧困、親や子どもの障害、虐待、ひとり親、不安定な家族関係、不安定な就労、健康問題、DV、地域からの孤立など、様々な要因が絡んでいる可能性がある。福祉の問題として取り組むべきである。
●P65〜、「施策の展開」に、社会問題化しているが、項目がない以下の項目を追加すべきである
「ヤングケアラー対策」
「子ども若者の自殺対策」
「性犯罪・性暴力対策」
●P66「ひとり親家庭への支援」
離婚後共同親権が昨年成立した。法施行は来年だが、Post-Separation Abuse(子に執着する別居親による離婚後の暴力、嫌がらせ、つきまといなど)が増加する懸念があり、今後は法律専門職への相談支援が、今まで以上に重要となると考えられている。そこで、「相談・情報提供の充実」のところは、下記の『』のような一文加えることが望ましい
「関係機関との連携により、学習支援や貸付金の事前相談及び申請手続きの補助等を行うとともに、『必要な法的支援が受けられるように』、ホームページや広報紙に相談機関等を掲載するなど、ひとり親家庭等を支援するための情報の周知を図ります。」
●P66 「ひとり親家庭等への支援」として「養育費確保支援事業」を追加すべきである。
養育費の支払いは未だに30%程度であり、ひとり親家庭の貧困の理由の一つは、親としての義務を果たさない別居親の存在がある。国も養育費支払いのための支援を進めていることから、項目として設けることは望ましい。
●p67 「いじめ防止対策推進」について
いじめの原因は、被害者・加害者の家庭の問題や、障がい、病気、貧困など様々な背景にある場合が少なくない。
啓蒙活動も大事であるが、その背景にある問題を解決することが必要な場合もある。特に加害者側の事情によるいじめは、啓蒙活動だけでは無くならない。対策として、いじめ防止等に係わる関係機関に限定せず、福祉・相談・医療機関など様々な関係機関との連携を図るべきである。
また、未然防止だけでなく、解決についても、学校だけではなく、町として取り組むと記載すべきである。
●P68 「子どもの貧困対策の推進」の「生活支援の推進」に、食糧支援の内容を設けるのはどうか。
現在町の社協では、フードパントリーやフードバンクを実施している。しかし、これれは、支援者と顔を遭わせなければならない支援のため、外聞を気にして、支援を受けたくないと考える人もいる。このため、こども宅食など、顔を合わせなくても良い支援をしている団体と協定を結ぶことも検討して欲しい。
●P69 「病児保育事業」
「事業を実施していません」とあるが、将来計画なので、「現在は実施をしていないが、実施を検討する」という記載にしてはどうか。
また、方法としては、他の自治体の設置機関に委託したり、他の自治体の施設を利用した場合に経済的支援をすることを検討してもいいと思う。
●P75 「継続的指導の充実」
乳幼児の検診に止まらず、就学前および就学後のデータの一元管理することで、継続的な支援を行うことを検討できないか。これは、「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について(令和3年12月21日閣議決定)」のP16「3)データ・統計を活用したエビデンスに基づく政策立案と実践、評価、改善」の項目にあるような、「情報を分析し、支援の必要なこどもや家庭のSOSを待つことなく、能動的なプッシュ型支援」を行うことを目的としている。