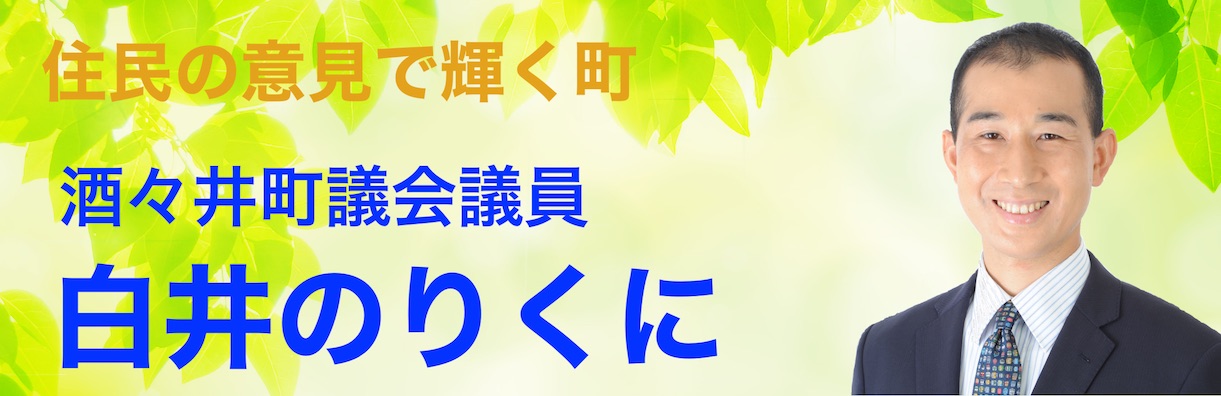通信制サポート校が、通学定期券の発売対象外に?
Xで、通信制サポート校が、通学定期券の発売対象外に?なるという書き込みを見た
詳しくは、一連にツリーを全部お読みいただきたいが、要約すると
- サポート校は、通信制高校の生徒の学習をサポートする民間の教育機関
- サポート校には、小中学性で不登校を経験したり、既存の公教育にマッチしなかった子どもも多く通っている
- 2022年、文科省が法令改正を行い、サポート校の位置付けを「面接指導等実施施設」「学習支援施設」などに分類
- 文科省の分類を受けた後、JRが「学習等支援施設」に通うことは、「通学定期券等の発売対象外」と規則を改訂
- 参議院予算委員会や内閣委員会で、この問題が何度か取り上げられたが、対象外という対応は変わらず
- なお、サポート校は「高校無償化」議論も、対象外
子どもには教育を受ける権利があります。
一般的な高校に通えない、特に小学校・中学校で不登校になった子どもが学ぶための場として利用されているサポート校の金銭的負担が増えることは、子どもの学びが困難にしてしまいます。
子どもの未来を守るために、何とかならないだろうか・・・
2025.03.19 以下を追記
以下、関連する国会での質疑を転載します
1.面接等指導等実施施設と学習等支援施設の切り分けと、通学用割引普通回数乗車券について
令和6年12月19日 第216回国会 参議院 内閣委員会 第3号
大島九州男 参議院議員の質疑
○大島九州男君 それでは、ちょっと次に積み残しをやらせていただきますが。
今資料を提供させていただいております。この資料、ちょっと先生方も見ていただいて、通信教育連携協力施設の類型というので、分校、協力校、技能教育施設、他の学校等の施設、サポート施設と、この部分が、文部科学省が法令の中で定めているこの通信教育に必要とする部分の面接指導等実施施設と学習等支援施設というふうな切り分けなんですね。その一番下にその他の施設というのがあって、これは別に学校が認めているところではないと。
だから、当然、この学校が認めているブルーの部分でやっているところに通う生徒については、今まで回数券なんか、通学定期も支給していたと。ところが、今回この面接等指導等実施施設と学習等支援施設を切り分けたから、だからJR東日本はこのサポート施設と言われるところに通う人には回数券出さないというふうに言っているんですよ。そういう通達出している。
だから、文科省としては、これを制度上切り分けたときにそういったことが起こるというのは想定していましたか。
○大臣政務官(金城泰邦君) お答えいたします。
そもそもこれを分けた背景としては、ウィッツ青山学園高校の事案を始めとした違法又は不適切な学校運営などがあったと。そういった背景から、高校教育の実施にふさわしい教育環境下で教育が受けることができるようにということで、令和三年三月に高等学校通信教育規程の一部改正を行いまして、面接指導等実施施設と学習等支援施設として法的位置付けを整理、明確化する、それが文科省の責任の中において取り組んできたということでありまして、定期の件をどうこうしたという、考慮したというものではございませんでした。
○大島九州男君 だから、そういうことは別に想定してやっているわけでも何でもなくて、JR東日本が、それをいいことに、こういうふうに分けたということなんですけど。
これ、学校側がどういうような見解を示しているかというと、学習等支援施設に通う生徒の通学定期への許容性に関する事情をしっかり理解してくださいよと。東日本はそんなこと言っているけど、ほかの鉄道会社においては、年齢が十八歳以下であれば無条件で通学定期を発行しているケースもあるんですよと。東日本さん、ちょっと頑張ってやってくださいよと。形式的に学習等支援施設に通う生徒のみ通学定期から除外するべき理由はないじゃないですかと。だから、ほかの会社もやっているんだから、貴社において可能なものと思料いたしますよと。
残念ながら、通学、要は通信に通う子供たち、通常家庭と異なり、通信課程に通う生徒に対しては、何らかの問題があるんじゃないかというふうに差別的な目で見られる現状があるんだと。これ、生徒の立場とかそういう学校が、やっぱりそういった見方をされる子もいるんだと。通常の学校に通う生徒と比較して経済的、社会的な不利益を生じさせるようなこういう決定は差別を生むことになりませんかと。だから、同じ高校生でありながら経済的な負担を強いるべきことは避けるべきであって、通学定期乗車券や学生割引回数乗車券を利用できる権利は、今まで認められていたのに、そうやってちょっと切り分けられたからといって剥奪されるものではないと思いますよと。どれだけ東日本がそれで収益が悪くなるんですかと、変わらないんじゃないんですかというふうな、こういう声がいっぱい上がっているんですよ。
国交省、これ、民間だから、いや、私たちは関係ないというんじゃなくて、どう思います、これ。ちゃんとJR東日本に、こういう要望があるんだったら聞いてあげたらどうですかと指導できませんか。
○大臣政務官(高見康裕君) お答えをいたします。
一義的には、学習等支援施設に対してこの通学用割引普通回数乗車券、販売するか、販売については、あくまで鉄道事業者の経営上の判断で実施できるものでございます。ただ、今、大島委員が一昨日と本日と問題意識を、特に現場でお困りの方の声も直接お聞きになった上で問題提起をされているわけです。
国土交通省としましては、一昨日にこの本委員会において委員から御指摘があったことを踏まえまして、学習等支援施設を通学用割引普通回数乗車券の発売の対象として継続することができないか、既にJR東日本にお伝えをいたしました。
ただ、繰り返しになりますけれども、本日の議論もまた踏まえまして、委員の問題意識につきまして、再度事業者に伝えたいと思います。
○大島九州男君 ありがとうございます。
国交省はすばらしいじゃないですか。文科省、国交省がこういうふうな形で申入れするんですから、文科省としては、私たちはそんな差別的なことで切り分けたんじゃなくて、それをそういうふうに運用するというのはいかがなものかというのをJR東日本に言えませんか。
○大臣政務官(金城泰邦君) お答えいたします。
JR東日本の事業は文科省が所管する事業ではございませんので、文科省としましては、これまでもやってきたように、国土交通省に対しまして、通学用の割引回数券の販売や通学定期券の要件の柔軟化などを、交通費負担軽減に係る配慮、それとともに各鉄道等の事業者に対する通知を、依頼する通知を発出している、こういったところが我々のできることかなと考えております。
○大島九州男君 じゃ、文科省から国交省にそういうのをお願いして、国交省がJR東日本に行くと、こういう理解でよろしいですか。はい、分かりました。
こう言うとあれなんですけど、別に私はJR東日本が嫌いとかそういうことじゃないですよ。前回、御存じの方もいらっしゃると思うんですけど、障害者の方が切符買うのに、今はネットでいろいろ買える「えきねっと」とかなんとかいうのがあるけど、障害者の皆さんはその証明書を持って窓口に行きなさいと。それおかしいだろうと。障害者の人たちはそういう扱いだったんだけれども、これ、国会でこういう問題になったら、ちゃんとできるようになったんですよ。だから、やればできるんですよね。だから、やる気があるかないかだ、それからまた、そういう意識があるかないかだと思うんですよ。
私が最初に問い合わせたときに、いやいや、そんな別に検討とかしていないですよとかいうのを軽くJR東日本は返してきた。それぐらい何の収益にも利益も関係ないようなことを、ただそういう制度が変わったからといって、子供たちの経済的負担のことを考えないで勝手に、ああ、もうこれ今まで曖昧だったけれども、こういうふうに切り分けたから、あっ、これでいいやなんていうふうにしてやろうとする企業の姿勢が気に入らない、私はね。だから、ちゃんとそこら辺は、この企業、東日本を支えている株主の皆さんがもっとしっかり物を言うべきですよ。収益にも関係ない。本来、会社というのは社会公益のためにあるものであって、株主のためにあるわけじゃないですよ。
お客様のためにあるJR東日本が、そういう子供たちの通学に関わる費用が、そして、今厳しい状況の中でちょっとでもやっぱり負担が増えるということを考えたら、そんな決定はできないというふうに私は思うので、今回、文科省から国交省、そして国交省から東日本に言っていただくことには感謝しますし、ちゃんとこれが結果として子供たちの不利益にならないようにしていただくまでしっかり言っていただくことを要望して、終わります。
2. サポート校が無償化の対象外の事に対して
令和6年12月18日 第216回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
阿部祐美子 衆議院議員の質疑部分
○阿部(祐)委員 一人一人の実態の把握というよりも、その経済的な負担の実態の把握をしてほしいという質問だったんですけれども、ちょっと分かりにくくて済みません。
それで、御答弁があったような私立の本校部分に対して支援がある、このことはもう十分承知しているわけで、ただ、やはり経済的負担が大きくなっているのはそれ以外の部分、連携あるいは提携、そしてサポートといったところが負担が大きくなっているわけで、そのことが、保護者や生徒にとっては、その御家庭にとっては結局は一体的な教育費として負担になっている、それによって教育へのアクセスがハードルができてしまっているという実態を問題視しております。
これに対して、文部科学省として何かできることはないかということでお伺いをしました。よかったら、大臣、お答えいただけますか。
○あべ国務大臣 サポート校を含む費用負担についての実態把握のところでございますが、サポート校は、いわゆる教育課程外の支援を行う施設でございまして、高等学校等の就学支援金の実は対象になっていないところでございます。
でも、本校に関わる授業料の部分は、先ほども政府参考人が説明をさせていただきましたが、この就学支援金による支援を行っている一定の負担軽減が図られているところでございまして、繰り返しになるところでございますが、いわゆる御指摘のサポート校を含む通信制の高校に関わる費用、学校や施設、また生徒によって様々でございまして、その実態の詳細について把握することは、今、大変困難なところでございます。
そうした中で、その様々なところの実態の詳細について把握することは本当に困難なところでございますが、御指摘を踏まえまして、私ども、また中で検討もしてまいりますが、非常に厳しい中でございまして、しっかりとその実態を把握することをすべきかどうかも含めて中で検討させていただきたいと思います。
○阿部(祐)委員 今、日本の高校生の十人に一人が通っている通信制高校ですから、その実態を是非踏まえていただきたい。十人に一人の子供たちが、どれだけの経済的な負担を持ってここに通っているのか。特に、不登校であった子供たち、あるいは非常に学校の中でケアが困難な子供たちの割合が多いとされている、そうした教育形態ですので、是非そこは取り残さないでいただきたいと思います。